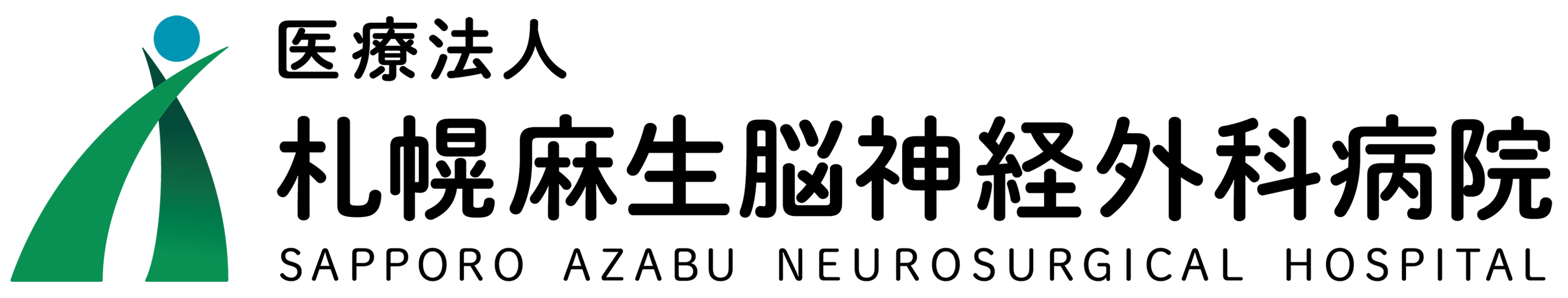看護部
メッセージ 麻生の看護 看護師採用案内 教育体制 看護部ブログ
麻生の看護
退院支援・退院調整
昨今、退院調整加算の引き上げや平均在院日数の短縮により、退院支援の必要性が高まっています。しかし、病院における退院支援の目的は経営的な視点ではなかったはずです。本来の退院支援は、疾患や障害を抱えながらも生活していた場に帰すこと、もしくは患者さま、御家族が望む生活の場を整える事にあったはずです。当院は脳神経外科の専門病院であり、脳卒中を筆頭に脳腫瘍、脊髄・脊椎疾患などの患者さまが来院、入院されます。程度の違いはありますが、麻痺や意識障害によって入院前に比べてADLが低下し、生活様式の再構築が必要な患者さまがおり、退院支援が必要になります。また、脳卒中を発症したけれど無症候性の(障害がない)患者さまもいます。その場合は自宅に帰れますが、退院支援が必要な場合もあります。なぜかというと、脳卒中は生活習慣病が発症の一因となることがあり、入院前の生活に何らかの問題を抱えていたことが示唆され、退院後にもとの生活に戻ると再発の可能性が潜んでいる場合があります。その場合も退院支援が必要なことがあります。
さらに、独居や必要な介護を十分に受けられない場合や社会資源を利用しないと在宅の移行が困難な場合など退院支援が必要な場合が多くあります。

看護師が退院支援をスムーズにおこなうための教育プログラムも組んでいます。演習で模擬合同カンファレンスを行い、地域のスタッフが病院側にどのような情報、介入を求めているのか、病棟看護師は入院中にどのような準備をして、どのような介入をおこなえば良いのかを学びます。また、模擬カンファレンスで患者さま役、御家族役になることもあり、どのような気持ちでカンファレンスに参加しているのかを感じる事もできます。
当院では、退院調整看護師を配置していません。もしかしたら、退院調整看護師を配置すると、今まで以上にスムーズな退院支援ができるかもしれません。しかし、「患者さまを生活の場に帰す」退院支援は、看護師の「患者さま、御家族に寄り添う看護」を実現できる場でもあります。「退院支援は難しいけど、楽しい」と看護師が言えるよう、そして、患者さま、御家族が望む退院後の生活が実現できるよう退院支援のシステムを構築しています。
ポディメカニクス(トランスファーテクニック)
ボディメカニクス(トランスファーテクニック)の意義
「ボディメカニクス」とは、体位変換や移乗移動動作のことをいいます。 ボディメカニクスの優れている点は、患者さま、看護師双方にとって安楽で安全に体位変換や移乗移動を行える点です。なぜそれが可能かというと、人間の起き上がる、立ち上がるといった動作はある一定の法則性があります。その法則を理解し、その動きに合わせて適切に介助することで、看護師の力で動かすのではなく、自然な動きで介助できるため、患者さま、看護師双方にとって安楽で安全に動かせることができるのです。
この技術は、遷延性意識障害、いわゆる植物状態の患者さまから筋力低下の高齢の患者さままで幅広く適応できます。刺激に反応せず、意識がないことで寝かせきりになっている患者さまであっても、この技術を使うことによって、積極的な離床を可能にさせます。一方、片麻痺があっても、意識がはっきりしていれば、患者さま自身の残された機能を使えば、全介助の必要はないはずです。必要最小限に介助しながら、生活の再構築という視点から、「生活を支える技術」としてボディメカニクスの技術を使って患者の生活の範囲を拡大し、食事・排泄・更衣・整容といった日々の活動を実現させています。 ボディメカニクスは、患者さまの持てる力を最大限に発揮させるためにも必要な看護技術と位置づけています。
もちろん、ボディメカニクスを体得するためには、それなりの訓練が必要です。いわゆる「コツ」というものになります。対象者の精神的身体的な機能を適切にアセスメントし、そのうえに立った介助方法を選択することが重要だといえます。個別的な差異をふまえたケアは、アセスメントの正確な目と実践の繰り返しが必要であり、技術体得のための研修を行っています。
この技術は、遷延性意識障害、いわゆる植物状態の患者さまから筋力低下の高齢の患者さままで幅広く適応できます。刺激に反応せず、意識がないことで寝かせきりになっている患者さまであっても、この技術を使うことによって、積極的な離床を可能にさせます。一方、片麻痺があっても、意識がはっきりしていれば、患者さま自身の残された機能を使えば、全介助の必要はないはずです。必要最小限に介助しながら、生活の再構築という視点から、「生活を支える技術」としてボディメカニクスの技術を使って患者の生活の範囲を拡大し、食事・排泄・更衣・整容といった日々の活動を実現させています。 ボディメカニクスは、患者さまの持てる力を最大限に発揮させるためにも必要な看護技術と位置づけています。
もちろん、ボディメカニクスを体得するためには、それなりの訓練が必要です。いわゆる「コツ」というものになります。対象者の精神的身体的な機能を適切にアセスメントし、そのうえに立った介助方法を選択することが重要だといえます。個別的な差異をふまえたケアは、アセスメントの正確な目と実践の繰り返しが必要であり、技術体得のための研修を行っています。