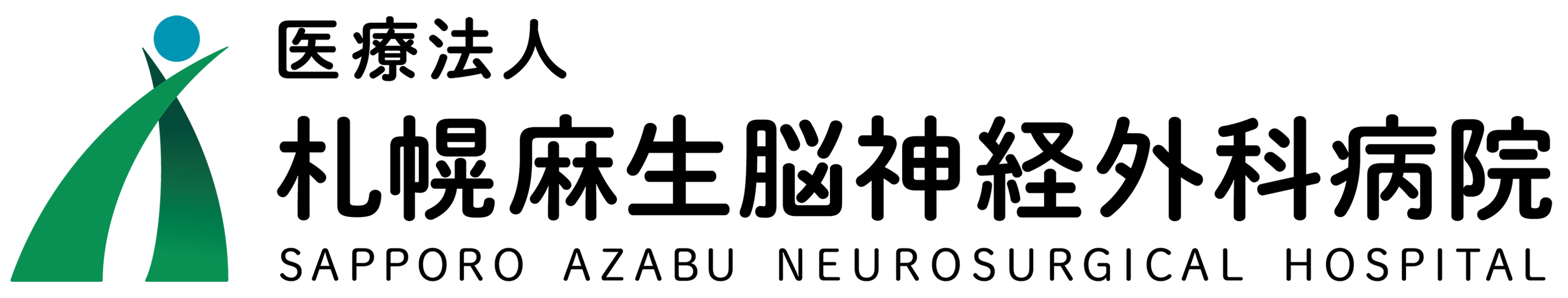機能外科センター
機能外科センターとは
2021年4月から機能外科センター長を担当する笹森より、当センターの診療内容を紹介させていただきます。神経に関わる病気やけがでは、適切な治療が行われた後も、全身の様々な部位に痛み・しびれ、つっぱりといった症状が残存することが珍しくありません。
前者は神経障害性疼痛、後者は痙縮と呼ばれます。これらの症状を有する方の生活の質(QOL)は、健常の方と比べ、著しく低下していることが知られ、適切な対応が求められています。
治療法として、まずは、各種鎮痛薬や抗痙縮薬の内服、ブロック注射、ボツリヌス療法等を行いますが、症状の改善が乏しい際に、ニューロモデュレーションと呼ばれる外科治療を検討します。
ニューロモデュレーションとは、神経に電気刺激や磁気刺激、薬物などを作用させて神経系の機能を調節する治療であり、当院では、神経障害性疼痛に対する脊髄刺激療法(SCS)、痙縮に対するバクロフェン髄注療法(ITB療法)を行っています。
SCSは、脊髄に微弱な電気刺激を加えることで痛みを緩和させる治療で、本邦では、1992年に保険適応になって以来、すでに30年以上の歴史がある治療です。近年、治療機器の改良に伴い、様々な刺激を実施することが可能となり、従来の刺激方法を上まわる有効性が多数報告されています。
ITB療法は、バクロフェンと呼ばれる抗痙縮薬をポンプとカテーテルを用いて、脊髄のくも膜下腔へ持続的に注入し、痙縮を緩和させる治療です。いずれの治療も痛みやつっぱりを完全に治すことはできませんが、症状を緩和することでQOLの向上を目指します。
機能性疾患について
前者は神経障害性疼痛、後者は痙縮と呼ばれます。これらの症状を有する方の生活の質(QOL)は、健常の方と比べ、著しく低下していることが知られ、適切な対応が求められています。
治療法として、まずは、各種鎮痛薬や抗痙縮薬の内服、ブロック注射、ボツリヌス療法等を行いますが、症状の改善が乏しい際に、ニューロモデュレーションと呼ばれる外科治療を検討します。
ニューロモデュレーションとは、神経に電気刺激や磁気刺激、薬物などを作用させて神経系の機能を調節する治療であり、当院では、神経障害性疼痛に対する脊髄刺激療法(SCS)、痙縮に対するバクロフェン髄注療法(ITB療法)を行っています。
SCSは、脊髄に微弱な電気刺激を加えることで痛みを緩和させる治療で、本邦では、1992年に保険適応になって以来、すでに30年以上の歴史がある治療です。近年、治療機器の改良に伴い、様々な刺激を実施することが可能となり、従来の刺激方法を上まわる有効性が多数報告されています。
ITB療法は、バクロフェンと呼ばれる抗痙縮薬をポンプとカテーテルを用いて、脊髄のくも膜下腔へ持続的に注入し、痙縮を緩和させる治療です。いずれの治療も痛みやつっぱりを完全に治すことはできませんが、症状を緩和することでQOLの向上を目指します。
機能性疾患について

機能外科センター長
笹森 徹
日本脳神経外科学会専門医・指導医
日本脊髄外科学会指導医
日本定位・機能神経外科学会技術認定医
日本脳卒中学会認定専門医
脊椎脊髄外科専門医